こんにちは。米農家に生まれ育ち、白ごはん大好き!な管理栄養士、shiro mama(シロママ)です。
2月3日といったら節分を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
毎年節分が近づくと、どんな具材で恵方巻きを作ろうかと考えるのが楽しみなshiro mamaです。
節分は2月3日と思われがちですが、2025年の節分は2月2日だったんです。
なぜ日にちが違うのでしょうか?
この記事では、【2025年節分の完全ガイド】恵方巻きの由来から今年の方角、節分の楽しみ方までとして、節分に関する知識や情報を紹介します。
この記事はこんな人におすすめ!
- 節分に関する知識を学びたい方
- 恵方巻きの楽しみ方を知りたい方
- 今年の方角を知りたい方
節分っていつ?2月3日じゃないの?
節分といったら2月3日のイメージですが、2025年の節分は2月2日でした。
なぜ、日にちが違うのでしょうか?
まず、節分は立春の前日と定義されています。
立春の日付は地球の公転周期(約365.2422日)と暦(365日)のズレを補正するため、年によって変動します。
このズレ補正により、2025年の立春は2月3日となり、その前日である2月2日が節分となります。
節分が2月2日となる理由は、この暦の調整サイクルによるものです。
2021年にも節分が2月2日となり、これは1897年以来124年ぶりの出来事でした。
同様に2025年も4年ぶりに2月2日の節分となりました。
このような調整は、季節と暦のずれを最小限に抑えるために必要な措置になります。
ちなみに2026年から2028年まで節分は2月3日
2029年、2033年、2037年は再び2月2日になります。
私も節分の日を直前まで間違えていて、2月2日当日にギリギリ気づきました…
節分の日を間違えないようにしたいですね。
恵方巻きの歴史と意味
どのようにして恵方巻きを食べるようになったのか、また恵方巻きの具材の由来を日本の食文化を通じて、深掘りしていきます。
恵方巻きの起源と発展
恵方巻きの起源は諸説ありますが、江戸時代末期から明治時代初期の大阪船場で始まりました。
当初は「丸かぶり寿司」や「太巻き寿司」と呼ばれ、商売繁盛や無病息災を願う風習でした。
1970年代にマスコミに取り上げられ、1980年代にコンビニエンスストアでの販売が始まり、全国的に広まりました。
7種の具材に込められる意味
恵方巻きの具材は、七福神にちなんで7つの具材を入れて巻くのが基本でした。
7種の具材には縁起の良い意味が込められています。
具材の意味
- 海老:長寿
- 穴子:富
- 昆布:健康
- れんこん:魔除け
- しいたけ:学問
- きゅうり:長寿
- ねぎ:勝負運
これらの具材は七福神にちなんで、縁起の良い一年を願う思いが込められています。
2025年の方角と食べ方
次に、恵方巻きの方角と方角の決め方、恵方巻きの正しい食べ方を紹介します。
2025年の方角と方角の決め方
2025年の方角は西南西でした。
これを恵方と呼び、恵方は十干(じっかん)に基づいて決められます。
十干(じっかん)は、古代中国で生まれた10の要素からなる順列システムです。甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10文字で構成されています。
2025年は「乙(きのと)」の年にあたるため、西南西が恵方となります。
恵方巻きの正しい食べ方とルール
- 節分の日(2025年は2月2日)に食べます。
- 恵方巻きは1人1本を用意し、切らずに食べます。
これは縁を切らないという意味があります。 - 西南西の方角を向いて食べます。
- 食べる際は願い事をしながら、黙って最後まで食べます。
話すと運が逃げてしまうとされています。
【その他の注意点やルール】
- 目を閉じて食べる、または笑いながら食べるという説もあります。
- 食べる時間に特定のルールはありませんが、豆まきで家の中を清めた後に食べるのがおすすめです。
- 子供や食べきれない場合は、小さいサイズや半分のサイズを用意するのがおすすめです。
節分の豆まきの歴史と意味
では、節分といったら恵方巻きと一緒に思い浮かぶ豆まきにはどのような歴史と意味があるのでしょうか?
正しい豆まきの方法についても紹介していきます。
豆まきの歴史
豆まきの歴史は古く、その起源は中国の古代の風習に遡ります。日本では平安時代に宮中で行われていた「追儺式(ついなしき)」が豆まきの原型となりました。
豆まきには、鬼(邪気)を追い払う意味と、豆を投げ与えて静めてもらうという二つの意味が込められています。
大豆は「魔滅(まめ)」に通じ、無病息災を祈る意味があるとされています。
現代では、節分の日に家族全員で豆をまき、自分の年齢の数だけ豆を食べる習慣が一般的になっています。これにより、一年の健康と幸福を願う日本の伝統行事として定着しています。
豆まきの方法
- 炒った大豆(福豆)を用意する
- 一家の主人や「年男」(その年の干支生まれの人)が豆をまく
- 「鬼は外、福は内」と唱えながら豆をまく
- 自分の年齢の数だけ豆を食べる(健康祈願)
現代における節分の過ごし方
現代の節分は、伝統的な豆まきに加えて、家族で過ごしたり、お祭りに参加したりという過ごし方が一般的になっています。どのような過ごし方があるのかを紹介します。
- 恵方巻を食べる:その年の恵方(縁起の良い方角)を向いて無言で恵方巻を丸かじりする
- 節分祭に参加:神社や寺院で行われる節分祭に参加し、厄除けや福招きを祈願する
- 家族で豆まき:家族全員で豆まきを楽しむ家庭も増えている
- 節分にちなんだ和菓子を楽しむ:吉祥豆や福豆などの節分にちなんだ和菓子を食べる
米農家の節分の過ごし方
節分の過ごし方の例として、米農家である実家の節分の過ごし方を紹介します。
節分といえば、焼いたイワシの頭を柊の枝に刺した「柊鰯(ひいらぎいわし)」を玄関に飾っていました。
柊は、棘の痛さで鬼を追い払うため、いわしの頭はその臭気で鬼を寄せ付けないようにという意味で魔除けや厄除けの意味しています。
馴染みがない方が多いと思いますが、茨城県の郷土料理である「しもつかれ」も節分の日の定番として、食卓に並んでいました。
お正月に食べた塩引き鮭の頭や、節分に煎った福豆の残りの大豆などの残り物を使い、野菜や酒粕、調味料で煮込んだものです。
また、家族で食卓を囲み、恵方巻きを食べ、豆まきをするのですが、豆まきの前に「みそかっぱらい」を行う風習もありました。
「晦日祓い」の意味で、祓え串で「みそかっぱらい」と言いながら神棚を清める事、そして各お部屋・家族などの厄や災いを祓い清める家長による屋敷祓いです。
年長の男性である祖父や父が行っている姿を見ていました。
地域や家庭により過ごし方が様々な節分ですが、各ご家庭の風習や楽しみ方を見つけられるといいですね。
まとめ
2025年の節分の完全ガイドでは、節分の日付や恵方巻きの由来、2025年の方角、豆まきの意味を解説しました。
節分は立春の前日で、2025年は2月2日が節分です。恵方巻きは大阪発祥で、7つの具材には縁起を担ぐ意味が込められ、今年の方角は西南西です。
食べ方には「黙って願い事をしながら食べる」ルールがあり、福を招くとされています。
また、豆まきは邪気を払い、健康と幸福を願う伝統行事で、家族で楽しむ現代の過ごし方も紹介しました。
ご家庭にあった楽しみ方で家族と一緒に節分を楽しみたいですね。
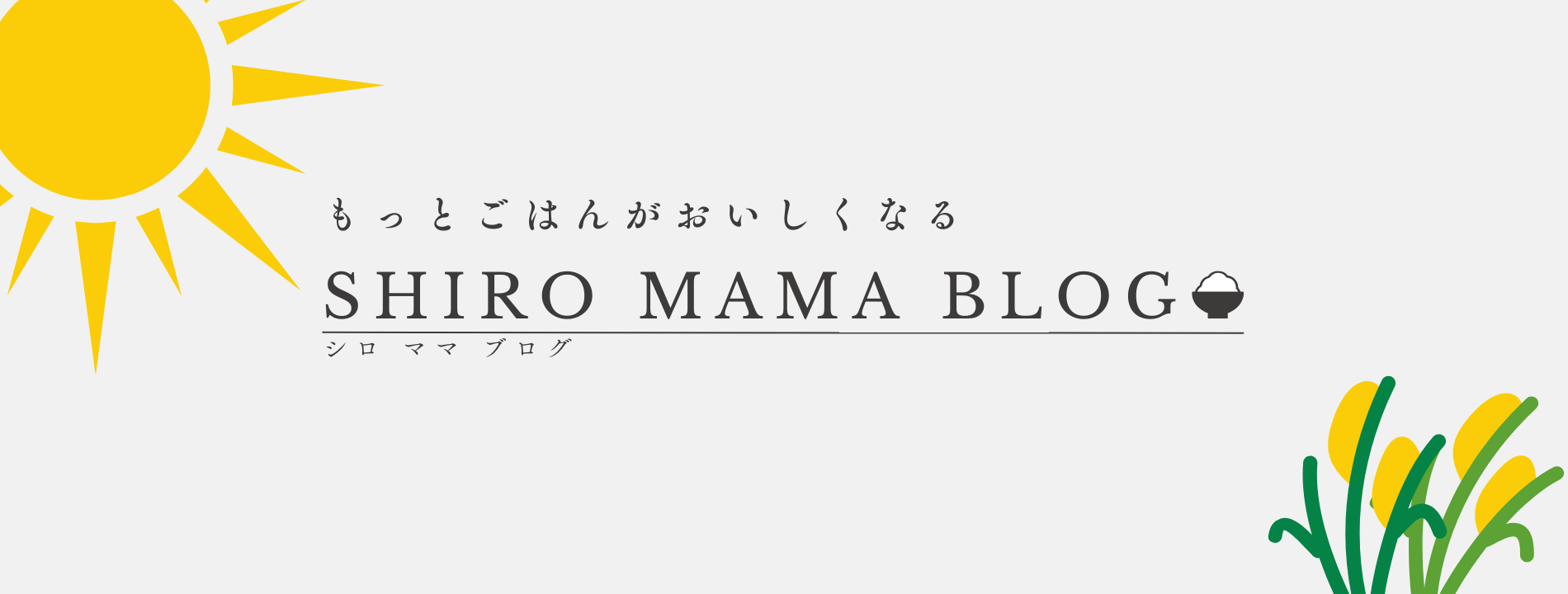



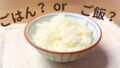
コメント